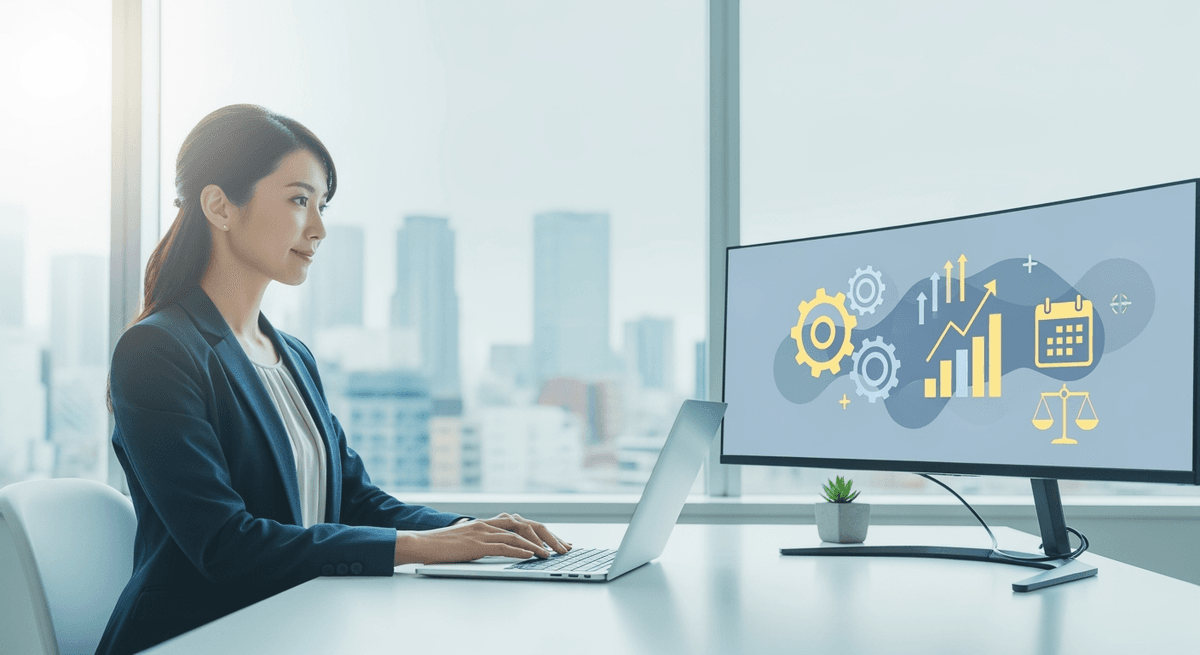会社員が守るべき「副業ルール」の全体像
最初に確認したいのは就業規則です。多くの企業は「事前申請・許可制」や「競合他社での就労禁止」「会社設備の私用禁止」などの条項を設けています。ここでのコアは、会社への忠実義務と利益相反の回避です。たとえ業務時間外であっても、会社の顧客情報やノウハウを用いた活動は守秘義務の観点から問題となり得ます。就業規則と雇用契約を読み合わせ、申請が必要か、禁止領域はどこか、許容される活動は何かを明確にしましょう。
競業避止・守秘義務・会社資産の私用禁止
副業で最も誤解されやすいのが「業務時間外なら自由」という考え方です。実務では、同業他社での就労や、現職の職務と密接に関連する請負は競業に当たるリスクが高くなります。判例でも、過度な競業禁止は無効となる場合がありますが、顧客引き抜きや社内情報の持ち出しといった行為は明確なルール違反です。また、自宅作業でも会社PCやライセンスソフト、クラウドストレージの使用は避けるのが安全です。境界線が曖昧だと感じたら、仕事内容を具体的に分解し、会社の事業との重なりを言語化しておくと説明しやすくなります。
成果物の権利にも目を向けてください。著作権や発明の取り扱いは、職務の範囲や就業規則の知的財産条項次第で帰属が変わります。たとえば勤務先の業務として作成したマニュアルは会社帰属が原則ですが、就業と無関係な時間に自らの道具と知見で制作したブログ記事やイラストは、一般に本人の権利が認められます。ただし、会社の機密情報を素材に使えば守秘義務違反になり得ます。
「申請・許可」はどこまで必要か
申請の要否は就業規則で決まります。許可制の会社で無申請のまま進めると、懲戒の対象になることもあります。一方で、ガイドライン型(届出のみ、一定条件を満たせば原則可)の企業も増えています。過度な制約は働き手のスキル形成を妨げるとして、厚生労働省も副業・兼業の促進に関するガイドラインを公表しています[3]。自社のルールを確認し、必要なら仕事内容・所要時間・報酬の見込み・利益相反の回避策を簡潔にまとめた書面を用意して申請すると、審査はスムーズです。
税金・社会保険・就業時間、誤解しやすい3つのポイント
副業を始めると、お金と時間のルールが動きます。ここでのキーワードは、所得区分、住民税、そして就業時間の通算です。いずれも「なんとなく」で進めると後から調整が必要になりがちですが、仕組みを知っておけば対応は難しくありません。
税金の基本:確定申告と住民税の扱い
副業がアルバイトのような雇用なら給与所得、業務委託や制作、講師、物販などなら雑所得または事業所得に区分されます。年末調整が完結するのは主たる給与のみで、それ以外の所得がある会社員は原則として確定申告が必要です[4]。よく話題になる「20万円ルール」は、給与の年末調整が済んでいて、かつ給与以外の所得が20万円以下なら確定申告を省略できるという取り扱いですが、住民税は別建てで申告が必要になる点に注意してください[5]。会社に活動を開示していない場合は、住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)に指定する運用が知られています。ただ、自治体の実務や金額次第で会社に通知される可能性はゼロではありません。隠す前提で設計するより、就業規則に沿って整えるほうが長期的には安全です。
業務委託で継続性があるなら、開業届と青色申告の検討も価値があります。帳簿付けは必要ですが、赤字の繰越や65万円の特別控除などのメリットが得られる可能性があります[6]。いずれも税制は変わるため、金額が大きくなったら最新の公的情報や税務署の案内を確認すると安心です。
社会保険と労災、そして「時間の通算」
社会保険は、雇用による副業を複数持つ場合に加入要件を満たすかどうかが論点になります。メインが被用者保険で、副業が個人事業のケースでは原則としてメインの保険を継続し、売上が伸びたからといって直ちに新たな社会保険に加入するわけではありません。一方、複数の会社に雇用されるケースでは、労災や給付の取り扱いに関する特例(複数事業労働者に関する制度)が導入されています[8]。事故や病気の備えは、制度の最新情報を必ず確認しましょう。
時間の通算は、もうひとつの盲点です。厚生労働省のガイドラインでは、労働基準法上の時間外規制や健康確保の観点から、副業先と元の会社の労働時間を通算して把握することが推奨されています[7]。現実には各社の管理に限界があるため、働く本人が週あたりの総労働時間と睡眠時間をセルフマネジメントすることが重要です。特に繁忙期に副業を積み増すと、長時間労働の扱いが複雑になります。健康診断での指摘やパフォーマンスの低下は、最終的に本業にも跳ね返ります。
守りを固めて始める実践ロードマップ
ルールの輪郭が見えたら、次は進め方です。いきなり売上目標を背負うより、まずは「安全に試す」段階を設けるのが現実的です。たとえば、平日夜に週1回・2時間の情報発信を3週間続けてみる、既存のスキルを使ったスポットの業務委託を1件だけ受けてみる、といったミニ実験から始めると、生活リズムや家族との調整の課題が浮かびます。
ここで有効なのが、活動を「価値」「リスク」「リソース」の3軸で棚卸しする方法です。自分のスキルが誰のどんな課題を解くのか(価値)、就業規則や競合リスクはないか(リスク)、週に何時間・何曜日なら無理なく確保できるか(リソース)を文章で書き出し、重なるゾーンを初手に選びます。価格設定も、時給換算・成果物単価・月額固定のいずれが本業と両立しやすいかで考えると、納期の遅延やクオリティの揺れを抑えられます。
契約とお金の段取りも小さく整えます。業務委託では、業務範囲、納期、検収方法、再委託の可否、秘密保持、知的財産の帰属、報酬の支払いサイトを文書で交わすのが基本です。見積書・請求書のフォーマットを先に用意し、提出タイミングを合意しておくとキャッシュフローが読みやすくなります。報酬が銀行口座に入ったら、すぐに帳簿に記録し、経費はレシートとセットで保管。これだけで確定申告の負荷は大きく下がります。
健康面は「無理をしない仕組み」を先に決めておきます。たとえば、睡眠が6時間を切る日が2日続いたら副業の作業を翌週に回す、週末のどちらかは完全オフにする、といった自分ルールです。各種調査では副業の作業時間は週5〜10時間がボリュームゾーンとされます[1]が、繁忙・閑散の波を見越してバッファを確保するほうが長持ちします。
ケースで考える:スキルは「今あるもの」から
抽象論を現実に落とし込むために、汎用スキルに目を向けます。資料作成、進行管理、ライティング、データ整備、顧客対応、オンライン講師などは、多くの職種で培われる力です。これらを「誰に」「何を」「どの形で」提供するかを絞れば、初回から大きな投資をせずに始められます。編集部にも、平日の夜に社外の勉強会で講師を務め、月に1回だけスライド監修の依頼を受ける、といった形で無理なく続けている例が寄せられています。量を追うより、信用を積む設計が本業との両立には有効です。
「バレない?」より「どう伝える?」の発想へ
会社に知られずに副業できるか、という質問はいつも上位に上がります。技術的には、住民税の普通徴収指定や、SNSの実名非公開、請負での取引などで「気づかれにくくする」ことはある程度可能です。しかし、就業規則に申請義務があるなら、無申請での継続はリスクが高いのも事実です。長く続ける前提なら、「伝え方」を設計するほうが健全です。
伝える際は、会社の利益と自分の成長が両立する絵を示します。具体的には、活動内容が会社の競合領域を避けていること、所要時間が本業に支障を与えない範囲であること、得られる知見を社内に還元できることを、簡潔に一枚で示すイメージです。承認者はリスクを最小化したいので、時間管理、情報管理、コンプライアンスの手当てが見えていると安心します。ダメな場合の代替案(活動の縮小、期間限定の試行、内容の再設計)も用意しておくと、前向きな議論になりやすいでしょう。
家庭やパートナーとのコミュニケーションも同じ構造です。家事・育児の分担、在宅作業の時間帯、連絡が取りづらい時間の共有など、生活の合意形成が進むほどストレスは減ります。副業は、お金以上に「時間と関係性の再設計」でもあります。ここを丁寧に整えた人ほど、続けられるという印象があります。
よくあるQのリアル:確定申告はいつ?どこまでが経費?
確定申告の期間は原則として毎年2月中旬から3月中旬です[9]。副業の種類によっては源泉徴収されていることもありますが、年末調整では完結しないため、集計と申告が必要になります。経費は「副業の収入を得るために直接必要な支出」に限られます。通信費や電気代のような家事関連費は、合理的な按分が求められます[10]。迷ったら領収書を保管し、メモを残すだけでも判断材料になります。
さらに学びを深めたい方は、社外の学び直しや資格取得の情報も参考になります。NOWHの関連記事「リスキリングの始め方」「時間管理の基本」「はじめての税金ガイド」「睡眠の質を高めるコツ」も、今日の一歩を後押しするはずです。
まとめ:小さく試し、誠実に続ける
副業はキャリアの停滞感を破る一手になる一方で、就業規則、税金、社会保険、健康管理の壁が並びます。だからこそ、就業規則の確認→小さな実験→記録と見直しという順番を守るだけで、安全性は大きく高まります。伝え方を整え、時間を守り、学びを循環させる。派手さはなくても、信頼は確実に積み上がります。
明日の自分を少しだけ軽くするために、今夜は申請の下書きを一枚作ってみる。週に2時間の作業枠をカレンダーに入れてみる。あなたの副業は、誰かの課題を静かに解き、本業の視野を広げ、生活のバランスを取り戻す手がかりになります。まずは小さく、でも確かに。あなたは何から始めますか。
参考文献
- パーソル総合研究所「副業の実態・意識に関する定量調査(2023年)」ニュースリリース https://rc.persol-group.co.jp/news/202310261000.html
- 厚生労働省「モデル就業規則」および改定情報(2018年) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221.html
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- 国税庁 タックスアンサー「No.1906 年末調整と確定申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.1900 確定申告が必要な人(20万円ルール等)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 厚生労働省「これってOK?副業・兼業(労働者向け学習ページ)」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_fukugyoutokengyou.html
- 厚生労働省「複数事業労働者に関する制度(労災保険等)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08778.html
- 国税庁 タックスアンサー「No.2024 確定申告の期間」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.2210 家事関連費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm