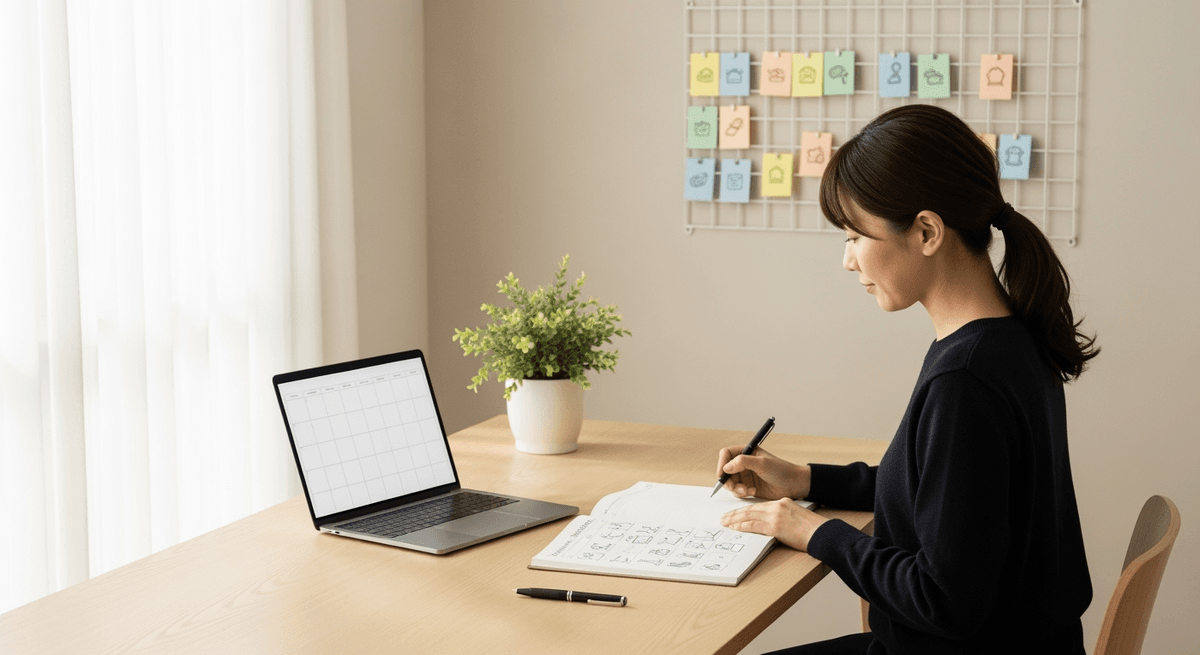家事ルーティン表が効く理由
統計によると、35〜44歳女性の無償労働(家事・育児・介護)時間は平日平均でおよそ4時間、同世代男性は約1時間台とされています(総務省「社会生活基本調査」等)[1]。なお、直近の全国データでは、全体平均で女性208分(約3時間28分)、男性44分/日(2016年、家事・育児・介護計)と報告されています[1]。国際的にも、アジア太平洋地域では女性は男性の約4倍の無償ケア労働を担うとILOが報告しています[4]。数字が示すのは「忙しさ」だけではありません。タスクの総量に加え、今日やることを毎回決める「意思決定の疲れ」も積み重なります[2]。編集部が各種データを見て実感するのは、量を減らす以前に、迷いを減らす設計が効くという事実です。そこで役立つのが家事ルーティン表。予定と習慣を一枚に可視化し、家族と共有するだけで、抜け漏れと衝突が目に見えて減ります。心理学の研究データでは、事前に「いつ・どこで・何を」まで決めておく実行意図(implementation intentions)が行動の実行率を高めることが示されています[3]。専門用語を並べなくても、要は**「悩む前に決まっている」状態**をつくること。それが、ゆらぎの大きい日々でも回る家事の土台になります。
家事のつまずきは、時間が足りないからというより、順番と基準が曖昧で「今は何を優先すべきか」を都度判断しているから生まれがちです。ルーティン表は、タスクと時間帯をあらかじめ結び付け、判断の回数を意図的に減らします。朝は弁当・洗濯・ゴミ出し、夜は食器・翌日の仕込み・洗濯の取り込みといった粒度で、やることが時間の器に収まっていれば、思考の迷いは大きく減ります。さらに、表に「下限」を書き込むのがポイントです。下限とは、忙しい日でも最低限ここまでで良いというライン。たとえば「掃除=床の見える部分だけ5分」「料理=主菜一品+カット野菜」など、頑張る日の理想形ではなく、崩れにくい標準形を定義します。これで自責感が和らぎ、翌日に回す決断も堂々とできます。
意思決定の疲れを減らし、時間の見取り図を作る
仕事の締切や子どもの予定、親の通院が重なると、とっさの判断はどうしても短期最優先になります。だからこそ、平常時に「時間の見取り図」を作ることが有効です。ルーティン表に、朝・昼・夕方・夜の4つの時間帯を置き、そこに反復する家事を配置します。週次の用事(生協の受け取り、資源回収の曜日、常備菜づくり)も、偏らないように曜日へ割り振っておきます。これで、カレンダーの予定を見た瞬間に、家事の大枠が連動して思い出され、アドリブの判断を減らせます。結果として、疲れ切る前に手が動くようになります。
見える化は、家族との分担交渉の前提になる
分担は、見えないままだと不公平になりやすいもの。ルーティン表は、担い手を「仮置き」しておけるので、家族会議のベースになります。たとえば、平日の朝に連なるタスクのうち、同時にできるものと順番が必要なものを分け、通勤時間や子どもの支度時間と重ねてみる。こうすると、朝の10分を確保できる人に「ゴミ出し+玄関の床拭きの下限」を任せ、在宅日の人は「洗濯機を回す→干すまで」を受け持つ、といった組み替えが現実的に検討できます。「誰が悪いか」ではなく「どの工程が詰まっているか」を見る視点が自然に生まれるのが、表の効能です。
家事ルーティン表の作り方
最初に白紙の紙、もしくはスマホやPCの表計算・メモアプリを用意します。横に曜日、縦に「朝・昼・夕方・夜」の時間帯を置くと、思考が整理されます。続いて、今やっている家事を思いつく順に書き出し、各タスクに「頻度」と「所要時間の目安」を付けます。ここは精緻さよりも手早さが大事です。朝の15分で終わることか、夜に回したほうが落ち着くことかをざっくり見極めながら、マス目に配置していきます。もし迷う場合は、ルーティンのトリガー(起点)を決めるのがおすすめです。起床したら洗濯機のスイッチ、帰宅したら弁当箱をシンクへ、食後30分で食洗機を回す、といった具合に、行動の流れに結び付けると記憶に残ります[5]。
30分で骨格を作る:下限と担当を仮置きする
完成度を求めすぎると進まないので、まずは30分で骨格を作ります。各時間帯に、絶対に外せないタスクを一つずつ置き、そこに下限を書き添えます。たとえば「朝の洗濯=洗うまで(干すのは夜でも可)」「夕食=主菜一品+味噌汁。副菜は余裕があれば」といった具合です。担当は仮で良いので名前を入れ、家族に共有してフィードバックをもらいます。ここで重要なのは、完璧な公平を目指すよりも、詰まりがちな時間帯の負荷を小さくすること。朝の渋滞をほぐせば、1日の体感が大きく変わります。
1週間運用して微調整:実態に合わせて軽くする
ルーティン表は、机上の計画で終わらせず、1週間で検証します。実際に回してみると、意外と時間がかかる工程や、逆に一緒にやると早い工程が見えてきます。たとえば「掃除は週末まとめて」よりも、毎晩のリセット5分を設けるほうが片付く家庭もあります。食材の下処理やゴミの日の準備を「移動のついで」に寄せるだけで、全体の滞留が減ることもあります。うまく回らない箇所は、タスクの粒度を小さくして下限を下げる、時間帯をずらす、担当を入れ替える、のいずれかで対応すると、表が現実に寄ってきます。
続けるための仕組み:崩れにくい設計へ
続けるコツは、頑張る日の設計ではなく、崩れた日の設計に力を割くことです。まず、忙しい日でも実行できる「ショート版」をルーティン表に併記します。夕食は丼や麺に寄せる、掃除はハンディ掃除機とウェットシートだけにする、洗濯は翌朝に回して睡眠を優先する、といった短縮ルールを先に決めておきます。これにより、夜遅くの自責感や衝動的な完璧主義を避けられます。さらに、1日2回のリセットタイム(たとえば朝出発前と就寝前に各5〜10分)を固定で入れておくと、散らかりの上限が下がります。リセットは「元の場所に戻す」「次に使う人のために整える」だけに絞り、掃除や片付けの評価軸を家族で共有しておくと、自然と標準がそろってきます。
道具も仕組みの一部です。紙派なら、冷蔵庫に貼るA4の週間表と、洗面所や玄関に小さなメモを置くと、見るべき場所で見るべき情報が目に入ります。デジタル派なら、家族で共有できるカレンダーやタスクアプリに、家事用のカレンダーを一つ新設し、繰り返し設定と通知を活用します。たとえば、資源回収や粗大ゴミの予約、回覧板の返却といった不定期タスクも、次回日付が決まった瞬間に入れておくと、表とカレンダーが連動して、先送りが減ります。どのツールを選ぶにせよ、**「誰が・いつ・どこで・何を・どこまで」**がひと目で分かることが決め手です。
実例イメージ:家族の1週間に当てはめる
たとえば、共働きの40代夫婦と小学生2人の家庭を想定してみます。平日朝は、起床から出発までの90分を3つのブロックに分けます。最初の30分は各自の身支度と朝食の準備。次の30分で食事と片付け、最後の30分でゴミ出し、洗濯機を回す、連絡帳と宿題の確認に充てます。ここでの下限は「食後のシンクに洗い物を残さない」「洗濯は回すまで」で十分。干すのは帰宅後に回しても、生活の質は大きく落ちません。夕方は、帰宅直後に弁当箱をシンクへ、手洗い後に冷蔵庫の在庫を見て主菜を決める、というトリガーを固定。調理中に子どもが音読をするなど、同時進行の工夫を組み込むと、待ち時間が学びの時間になります。就寝前は10分のリセット。各自が自分の机とリビングの自分ゾーンを整え、翌朝のカバンを玄関近くに置くところまでを到達点とします。
週末は、買い出し・作り置き・掃除の重たい工程が重なりがちです。ここでも下限を設けます。買い出しは1店舗で済ませ、足りないものは平日にネットで補う。作り置きは、主菜2品と茹で野菜・味玉のベースづくりだけに絞り、足りない日は冷凍うどんや豆腐、缶詰で変化をつける。掃除は「床の見える面積を広げる」ことをKPIにして、収納の精緻化は繁忙期が過ぎてからにする。こうしてルーティン表に「週末の上限」を書いておくと、やり過ぎによる疲れを防げます。
フォーマットと見せ方:紙でもデジタルでも
紙の週間表は、視認性が高く、家族全員の目に触れるのが利点です。色分けは担当者ごとよりも、時間帯や状態(準備・実行・片付け)で分けると、流れが掴みやすくなります。デジタルなら、カレンダーの色分けを担当者で分け、家事カレンダーだけをON/OFFできるようにしておくと、仕事との切り替えがスムーズです。写真やスクショを家族のグループに固定表示しておけば、場所に縛られず参照できます。いずれにせよ、更新が重荷にならないことが最優先。完璧なテンプレートを探すより、手元の用紙やアプリで今日から動かすほうが成果につながります。
まとめ:今日の30分が、明日の余白をつくる
家事はゼロにできないけれど、迷いや衝突は減らせます。ルーティン表は、忙しさの正体を見える形にし、家族で共有できる言語に変えるツールです。まずは30分で骨格を作り、1週間動かして微調整し、下限とショート版で崩れにくい設計にする。この小さな設計の積み重ねが、あなたの時間と気持ちに余白を生みます。「頑張れるときに頑張る」ではなく、「頑張れない日にも回る仕組み」を置くと決めたその日が、暮らしの転換点です。明日の朝、どの時間帯から整えてみますか。冷蔵庫に一枚の週間表を貼る、カレンダーに家事カレンダーを1つ作る。できるところから、始めてみましょう。
参考文献
- 内閣府 男女共同参画局. 男女共同参画白書 令和2年版(第1部)「家事・育児・介護時間の推移」. https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html
- Pignatiello GA, Smallheer BA. Decision Fatigue: A Concept Analysis. Nursing Forum. 2018. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6119549/
- National Cancer Institute (NIH). Implementation Intentions. https://cancercontrol.cancer.gov/brp/research/constructs/implementation-intentions
- International Labour Organization (ILO). Women do 4 times more unpaid care work than men in Asia and the Pacific. https://www.ilo.org/resource/news/ilo-women-do-4-times-more-unpaid-care-work-men-asia-and-pacific
- (J-STAGE)習慣形成と行動介入に関するレビュー(例:身体活動の継続と習慣化). Human Behavior Studies, 21(1). https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbs/21/1/21_1/_article/-char/ja/