
年齢別の「毎月いくら」をつかむ
文部科学省「子供の学習費調査」では、公立小学校の学校関連費は年間およそ30〜40万円、公立中学校はおよそ45〜60万円、私立小学校は年間150万円超という結果が示されています。[1] さらに大学では、国立大学の学納金は4年間でおよそ240万円、私立大学では文系で400万円前後、理系では500万円超が目安とされます(いずれも統計に基づく概算)。[2] 編集部が各種データを横断してみると、支出の「山」は幼児期の保育関連費、小4〜中3の学習費の伸び、そして高3〜大学入学時に集中する傾向が明確でした。
この「山」を前もって見取り図にしておくことができれば、気持ちにも家計にも余白が生まれます。専門用語は使いません。家計簿が苦手でも取り入れやすい形で、年齢別に毎月いくらを用意したいか、受験年にどれだけ上振れしやすいか、進路別に合計いくらを見ておくかを、今日から動けるレベルにかみ砕いてお伝えします。
まずは月のキャッシュフローの感覚をつかみます。ここで扱う金額は、食費・日用品・衣類などの生活費に加え、年払いの費用を12で割って月額換算した実感ベースの目安です。住居費やクルマ代のように家庭差が極端に大きい固定費は除き、制度の有無で変動する保育料・給食費・塾費などは代表的なレンジで表しました。地域や選択によって幅が出る前提で読んでください。なお、目安作成にあたっては公的な家計統計も参照しています。[5]
0〜2歳:現金フローが勝負の時期
この時期はオムツ・ミルク・ベビー用品の初期投資に加え、保育を利用するかで月の負担が大きく変わります。無償化の対象であっても給食費や延長保育、認可外を活用する場合などは自己負担が発生します。[4] 編集部の試算では、生活費込みで月2万〜4万円程度+保育関連で0〜3万円ほどが目安。復職直後の衣替えやベビーカー、チャイルドシートが重なる年は一時的に上振れします。児童手当が家計の緩衝材になりますが、消費に流すのではなく毎月1万円を別口座で確保できると、入園・進級の支払いに効きます。[3]
3〜5歳:無償化の安心と、行事・習い事の芽
幼児教育・保育の無償化で保育料の自己負担は原則ゼロですが、給食費や行事費、送迎の交通費などは実費です。[4] 好奇心が広がり習い事を始める家庭も増えるため、生活費込みで月2.5万〜4.5万円+任意の習い事・行事で0.5万〜1.5万円が実感に近いレンジ。卒園・入学に向けて、制服・学用品・学童入所関連の支出が重なるため、年長の秋からは**「入学準備」用に月1万円**のつみたてを意識したい時期です。
小学生:前半は穏やか、後半から上向き
公立小の学習費は統計上で年間30万円前後が目安です。[1] 前半(小1〜3)は学童の利用有無で差が出やすく、月1.5万〜3万円+学童で0.5万〜1.5万円という感覚に落ち着く家庭が多い印象です。後半(小4〜6)は修学旅行・高学年の校外活動・タブレット関連・塾の体験参加などで、月2万〜3.5万円+塾・通信教育で0.5万〜1.5万円にシフトしがちです。小6の秋以降は受験の有無に関わらず模試や講座で一時的に支出が増え、年トータルで**+5万〜15万円**の上振れを見込むと安全です。
中学生:部活×塾×交通費でピークが見え始める
公立中の学習費は統計で年間45〜60万円程度。[1] 部活の用具・遠征・大会応援に、通塾や定期テスト前の追加講座が重なります。編集部の試算では、月2万〜4万円+塾で1万〜3万円+交通費や大会関連で0.5万〜1万円がボリュームゾーン。中3は模試・受験料・私立併願の納付などが集中し、年合計は平年比+10万〜30万円を見込むと慌てません。スマホ・通信費の増加もこの時期から目立つため、家族のプラン見直しは早めに。
高校生:活動の幅が広がるぶん、変動も大きい
公立高の学校関連費は年40万円台が一般的ですが、私立高や専門的な活動を選ぶと一気に変わります。[1] アルバイトを始めると収支は軽くなる一方、定期代・検定料・修学旅行・受験準備の外部講座などで、月2万〜4万円+受験準備で1万〜3万円の感覚に。高3の秋からは受験料と交通・宿泊、入学金・前期納付金の一時払いが続くため、高1の春から「入学金用」に月1〜1.5万円を別建てで積み上げるとダメージが和らぎます。
大学進学直前〜在学中:まとまった学費と生活費
大学の学納金は、国立で4年間約240万円、公立で270万円前後、私立は文系で400万円前後、理系で500万円超が統計の目安です。[2] 自宅生なら通学費・教材費の上乗せ、ひとり暮らしなら家賃・光熱費・食費で月6万〜10万円の追加が見込まれます。入学時は入学金・前期授業料・機器購入(PCなど)がまとまって発生するため、高3夏までに「入学時一時金」30万〜50万円を用意しておくと、奨学金や教育ローンに頼る割合を下げられます。
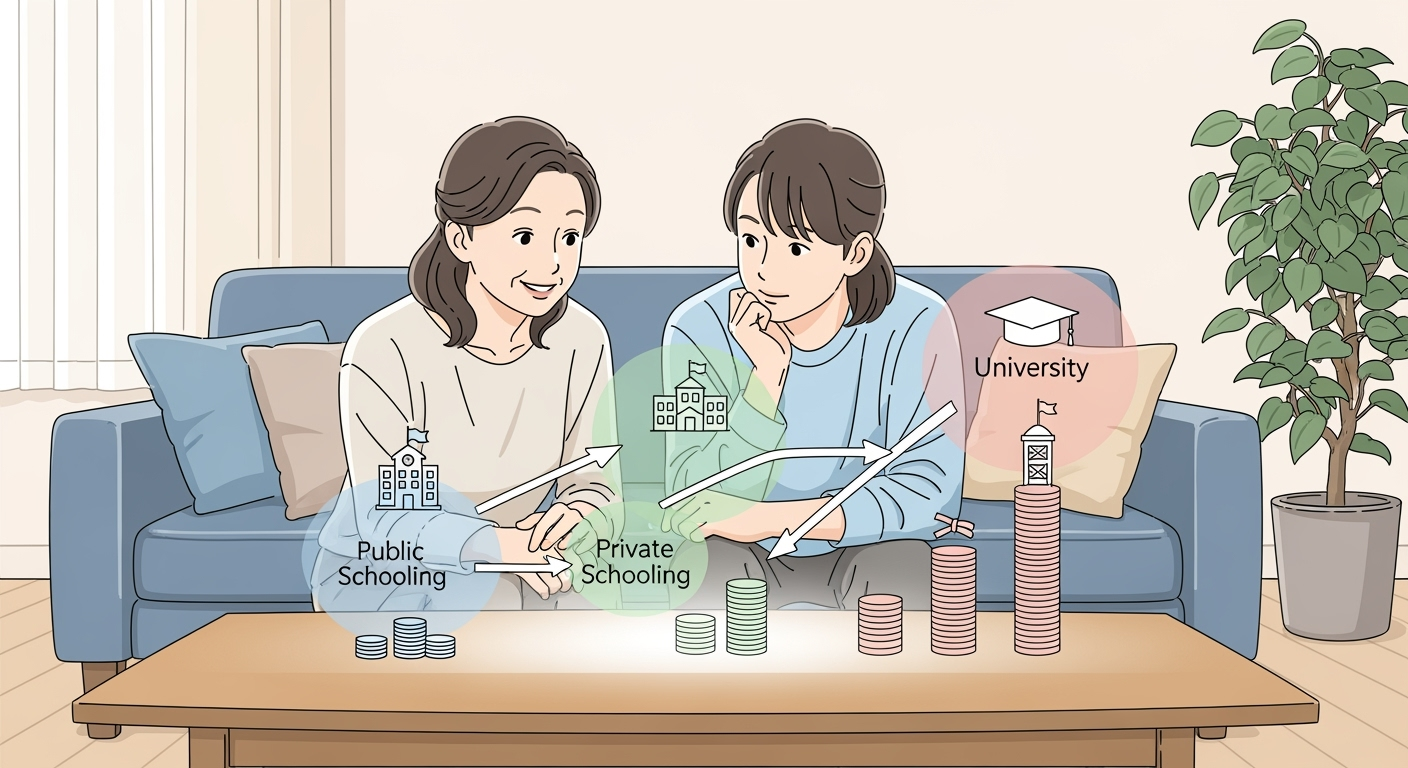
進路別合計のざっくり感覚を持つ
合計額は「教育費だけ」か「生活費も含むか」で大きく変わります。ここでは学校関連費(授業料・学校納付金・塾等)を中心に、一般的なレンジを示します。前提はすべて概算であり、自治体の補助や家庭の選択によって増減します。
まず、義務教育期間をすべて公立にした場合、小・中・高の学校関連費合計はおおむね150万〜200万円台後半に収まるケースが多い印象です。ここに大学を国立で進学すると学納金約240万円が加わり、合計で400万〜500万円台がひとつの目安になります。次に、小中は公立・高校だけ私立という進路では、高校3年間での負担が大きくなり、全体では600万前後になる組み合わせが見えます。中高一貫の私立に進むと、6年間の納付金・活動費で一気にレンジが広がり、大学が私立文系なら合計900万〜1,100万円、理系なら1,000万〜1,300万円程度を意識しておくと、資金計画の視界がクリアになります。
「教育費以外」も含めた養育費全体(食費・日用品・被服・通信・イベント)まで視野に入れると、出生から高校卒業まででおよそ1,000万〜1,500万円という実感値に近づきます。ここは各家庭の価値観と地域差が大きい領域です。大切なのは正確さよりも、自分の家庭にとっての現実的なラインを早めに言語化し、毎月の仕組みと連動させることです。

年齢別に効く「お金の整え方」
数字を眺めただけでは家計は動きません。年齢ごとに効きやすい打ち手を、暮らしの流れに合わせて整えていきます。乳幼児期はまず現金フローを安定させます。児童手当は拡充され、対象年齢の広がりと第3子以降の増額などが進みました。[3] 家族構成にもよりますが、年間12万円前後を手当として受け取るケースが一般的です。[3] このお金は**「使う口座」に入れず、「教育費口座」に直行**させるだけで、入園・進級・行事の支払いが驚くほどスムーズになります。幼児教育・保育の無償化も使い倒しましょう。保育料が原則無償でも、給食費や行事費は実費であることは忘れずに。[4]
小学校以降は、年払い・学期払いのイベントに備えて先回りします。ランドセルやタブレット購入、修学旅行の積立、部活の用具入れ替えなどは、家計簿がなくても予想できます。編集部のおすすめは、「使う」「守る」「増やす」の3口座仕分けです。給与は「使う口座」に入り、固定費と生活費へ。次に毎月の定額つみたてを「守る口座」(1年以内に使う目的別貯金)と「増やす口座」(3年以上の長期運用)へ自動で流すようにしておけば、学年のイベントが来るたびに右往左往する回数が減ります。
中学・高校では、通信費・サブスク・定期代といった固定費も見直しどきです。家族のデータ使用量を半年ごとに棚卸しして、不要なオプションを外す。保険は、子どもの医療費助成の範囲と公的保障を確認し、重複部分を削る。これだけで月3,000〜5,000円は生まれ変わる家庭が珍しくありません。受験が近づいたら、塾の講座を「全部のせ」にする前に、学校の過去問・内申の取り方・弱点教科の優先順位を家族で言語化してから投資するのが、家計的には合理的です。
大学資金は、親名義の新NISAなど長期・分散・積立の考え方がはまります。[6] 18年という時間を味方にできる幼少期は、月1万円の積み立てでも年15万円の入学時一時金に匹敵する効果を持ちます。ジュニアNISAは終了しましたが[6]、親の枠で目的別につみたてる発想は変わりません。学資保険を選ぶ場合は、返戻率だけでなく、払込免除の条件と受け取り時期の自由度を確認しましょう。奨学金と教育ローンは、在学中の返済シミュレーションを卒業後の初任給レンジと並べて確認し、「借りるならいくらまで」を明文化してから申し込みに進むと安心です。[7]

家族の見取り図を作る:3つの実践
計画の核心は、完璧な予算表ではなく、迷わないためのルールです。まず、年齢別の「上振れ月」をカレンダーに書き込みます。入園・入学、修学旅行、部活の大会、模試・受験料、入学金や前期納付といったタイミングが、あなたの家計にとっての要注意ポイントです。ここから逆算して、例えば**「高1から月1.2万円を入学金用」「小5から月5,000円を修学旅行・卒業関連」**のように目的別につみたてを割り振っていきます。
次に、毎月の生活費と教育費の仕切りをはっきりさせます。やり方はシンプルで、学校や塾の支払いをすべて「教育費口座」から引き落とすだけ。キャッシュレス払いでも、チャージ元を教育費口座に固定すれば管理は格段に楽になります。残高が視覚化されると、模試や講座の追加を決めるときの判断基準がブレません。
最後に、半年に一度の「家族ミーティング」を入れて、使途と優先順位をアップデートします。子どもが何に時間と情熱を注いでいるのか、何を諦めて何を選ぶのか。ここが言語化されるほど、お金の使い方に納得感が生まれ、「払ってよかった」支出が増えます。進路や活動の選択は家族のプロジェクトです。家計の透明度が上がると、子ども自身の金銭感覚の成長にもつながります。

まとめ:数字に怯えず、家族の優先順位へ
統計の数字は大事ですが、私たちが向き合うのは生きている家計です。年齢別の目安を知れば、次の山が怖さではなく道標になります。今日からできることは、児童手当の自動振り分け、教育費口座の開設、そして目的別の少額つみたて。この3つだけでも、来月の安心感は変わります。迷いが出たら、家計簿を続けるコツを見直し、固定費なら保険の見直しや通信費の最適化、長期の準備なら新NISAの基礎[6]や教育費準備の始め方も参考になります。
きれいごとだけでは回らない毎日の中で、数字はやさしい道具になれます。 家族の今と向き合いながら、必要なときに必要なだけのお金が届く仕組みを、今日の一歩から一緒に育てていきましょう。
参考文献
- 文部科学省. 子供の学習費調査. https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/006/05120501/003.htm
- 文部科学省. 私立大学等の授業料等の状況. https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00005.htm
- こども家庭庁. 児童手当のご案内. https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
- 内閣府. 幼児教育・保育の無償化. https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/youji-mushouka/index.html
- 総務省統計局. 家計調査. https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html
- 金融庁. 新しいNISA. https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/
- 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO). 奨学金制度. https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html











