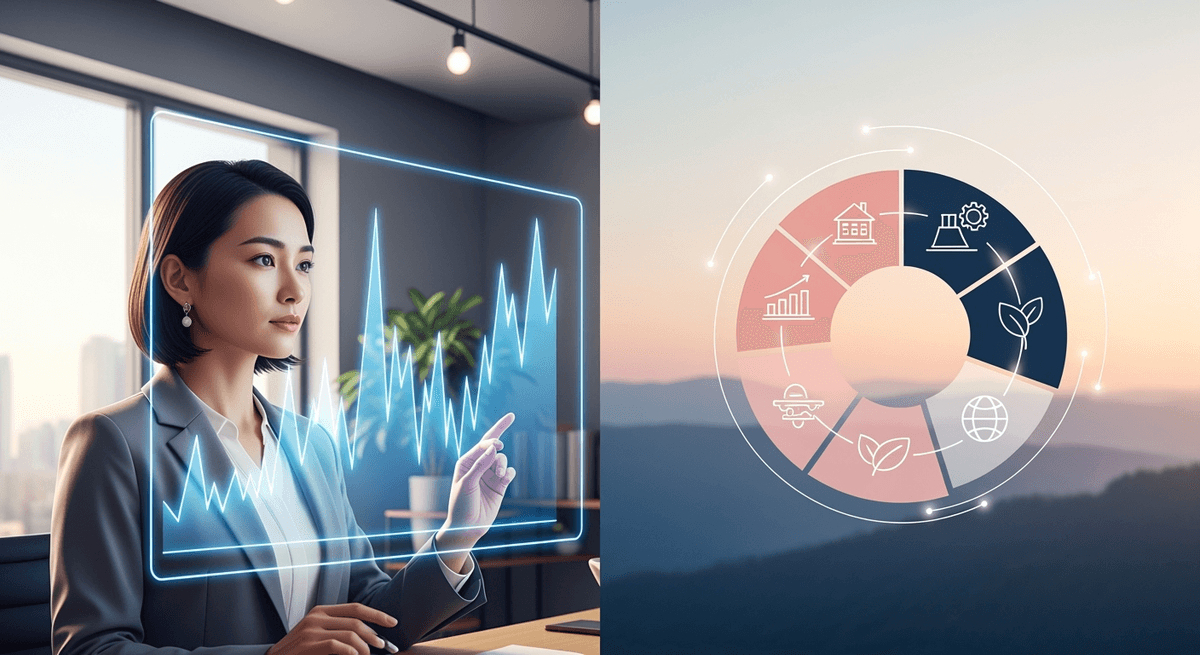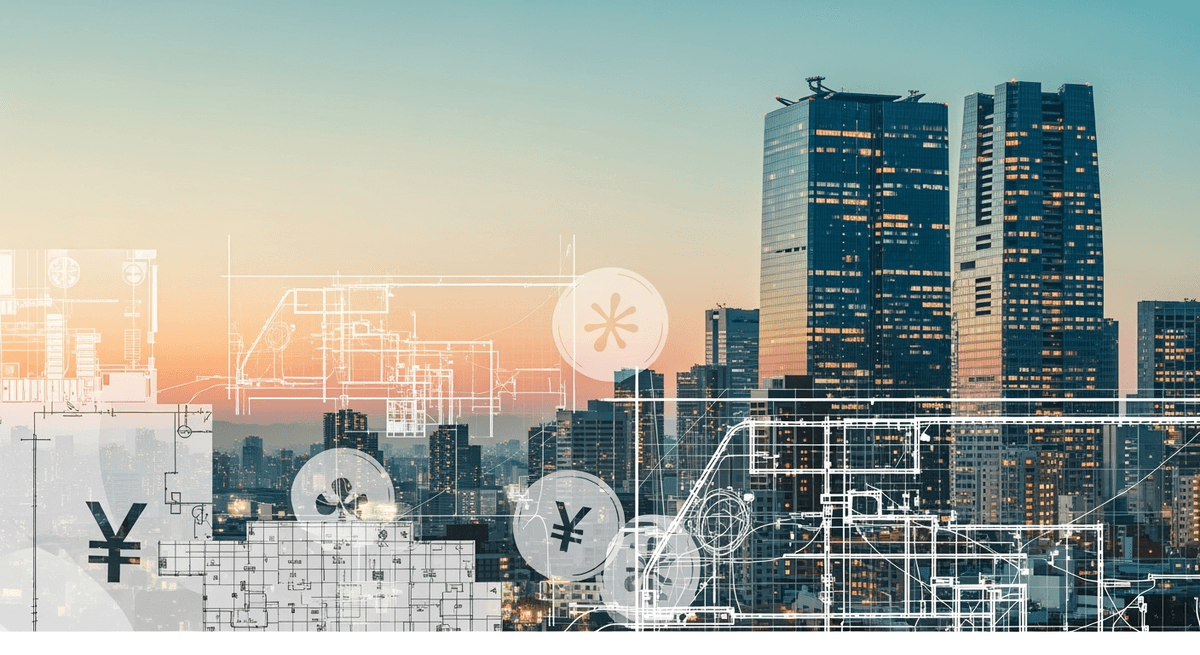データで読む「65歳以降も働く」現実
統計によると、日本の高年齢就業は世界的に見ても高い水準です[1]。背景には人手不足や就業機会の拡大に加え、長寿化による生活費の延伸があります。医学文献や経済学の研究では、仕事を通じた適度な社会参加が認知機能やメンタルの維持に寄与する可能性が指摘される一方[5]、過度な長時間労働は健康リスク(脳卒中や虚血性心疾患の死亡リスク上昇)を高めるとされ[6]、量と質のコントロールが重要だと示唆されています。つまり、65歳以降も働く選択は「フルタイムで走り続ける」か「完全リタイア」かの二者択一ではなく、時間や役割をチューニングしながら続けるグラデーションの設計が現実的です。
もう一つの現実は収入の形の変化です。退職金や年金の受給が始まる年代に、労働収入が加わることでキャッシュフローは厚くなりますが、税と社会保険、そして在職老齢年金の仕組みにより、総収入がそのまま可処分所得に置き換わるわけではありません。編集部が制度改正の流れを追うと、働き方の柔軟化と同時に、年金と賃金のバランス管理がいっそう求められるフェーズに入っています(65歳以上では賃金と年金の合計が一定額を超えると年金の一部が支給停止となる)[8]。
お金の設計図:年金・税・社会保険を味方に
まず年金です。老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳からですが、受給開始を早めたり遅らせたりでき、繰下げ受給は1カ月あたり0.7%増額される仕組みです。65歳から70歳まで待てばおよそ42%の増額、上限の75歳まで待てば最大で約84%増というインパクトになります[7]。研究データでは「いつまで生きるか」という不確実性を前提に、長生きリスクに対する保険として繰下げの価値が議論されています。ただし、現役収入や貯蓄、健康状態、家族の事情によって最適解は変わります。たとえば65歳からほどほどに働いて現金収入を確保し、70歳で年金を増額して受けるといった分散案は、取り崩しリスクを抑える現実的な選択肢になります。
次に、働きながら受け取る年金の調整である在職老齢年金です。制度上、65歳以上で賃金と年金の合計が一定額を超えると年金の一部が支給停止となります。基準額は近年見直しが続き、65歳以上では賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が47万円を超えると調整がかかる枠組みが目安です[8]。なお、支給停止された分が後から支払われるわけではありませんが、65歳以降も厚生年金に加入して働いた期間がある場合は、在職定時改定により毎年の年金額に反映される仕組みがあります[9]。つまり「損しかない」制度ではなく、時間軸で見る視点が必要だということです。賃金・賞与の見込みと年金見込額を並べ、どの範囲で働くのが家計にとって最適か、表面的な手取りだけでなく生涯収入で吟味しておきましょう。年金の基礎は、編集部の解説「年金のきほんと設計のコツ」も参考になります。
社会保険の加入も押さえどころです。厚生年金は原則70歳未満が被保険者であり[11]、75歳になると医療は後期高齢者医療制度へ移行します[10]。パートタイムでも、週の所定労働時間や月収の基準、事業所の従業員数などの条件を満たすと社会保険加入となるケースがあり、適用拡大の流れは続いています[12]。加入は保険料負担が生じる一方で、手厚い保障や将来年金の加算につながります。税では、公的年金等控除や各種控除があるため、給与・年金・資産収入の組み合わせで課税所得がどう変わるかを年単位で試算しておくと、働く強度や受給タイミングの決め方がクリアになります。副業やパラレルワークを組み合わせる場合は、住民税の通知や確定申告の手順もあわせて確認しておくと安心です。実務面の基本は「副業・パラレルワークの始め方」にまとめています。
資産運用とのバランスも、65歳以降の働く選択を左右します。2024年に制度が刷新された新NISAは年齢制限がなく、非課税での資産形成と取り崩しを柔軟に設計できます[13]。市場の変動と取り崩しが重なると資産寿命が縮むという「順序リスク」を和らげるために、65〜70歳の数年間を軽く働いて現金収入を確保し、取り崩しペースを抑える発想は合理的です。運用の考え方は「新NISAでの長期・分散・取り崩し設計」で詳しく解説しています。
働き方の選択肢とキャリアの再設計
65歳以降の働き方は、フルタイム継続だけではありません。同じ会社で短時間の嘱託として関わり続ける方法、専門スキルを活かして顧問・フリーランスとしてプロジェクト単位で働く方法、地域の有期雇用や非営利の場に軸足を移す方法、オンラインでの教育・支援に転じる方法など、選択肢は想像以上に多様です。研究データでは、仕事の自律性や貢献実感がウェルビーイングを高めるとされ[14]、役割を小さくしても裁量を確保できる働き方は満足度が上がりやすいという示唆があります。だからこそ、肩書や年収の大きさだけでなく、どの程度の時間配分で、誰の役に立てるのかという視点を持つことが、続けやすさの鍵になります。
40代のうちにできることは想像より具体的です。最初に、65歳時点で「週にどれくらいの時間で、どのテーマに関わりたいか」を言語化します。次に、その働き方に必要なスキルや信用を分解し、現在の業務の中で積み上げられる小さな実績を設定します。そして、社外の小さな仕事や登壇、資格を通じて「外で通用するプロフィール」を少しずつ育てます。流れはシンプルですが、10年単位で効いてきます。キャリアの棚卸しと目標設定の型は「強みの棚卸しワーク」を使うと取り組みやすくなります。
編集部では、マーケティング職のAさん(42歳)をモデルに、ラフな設計図を描いてみました。Aさんは、会社ではブランド戦略を担いながら、社外では地域の小規模事業者に対する広報アドバイスを月に数件受けています。55歳までにプロジェクトマネジメントとデータ分析の資格を取り、60歳からは週4日勤務に変更して、週1日は有償の社外案件に充てるプランにしました。65歳時点で会社とは週3日の嘱託契約、社外のコンサルを週1日という構成に移行します。収入は、嘱託が月14万円、社外案件が月6万円、合計20万円を目安に設計。年金は65歳からの受給を見送り、70歳で受け取る選択にすることで、月額の年金が約42%増になる見込みです[7]。60〜69歳は新NISA枠で積み上げた資産の取り崩しを最小限に抑え、70歳以降は年金の増額でキャッシュフローに厚みを持たせる。時間は1日に長くても6時間、通勤は混雑を避ける時間帯に限定。Aさんが重視したのは、手取りの最大化よりも、時間の自律性と健康の余白でした。数字と生活の折り合いを早めに考えておくと、選べるカードが増えることを、Aさんの設計は教えてくれます。
企業に残る選択をする場合は、評価の軸が若い世代と変わることを前提に、組織の「ミドル以降の役割定義」を確認しておくと迷いが減ります。後進育成や業務の仕組み化、品質管理といった領域は年齢を重ねるほど価値が高まりやすく、成果の可視化と引き換えに時間の柔軟性を得る交渉もしやすくなります。社外で働く選択なら、案件の振れ幅に対応するために固定費を抑える生活設計が効いてきます。いずれの場合も、65歳以降の働く選択は「誰と」「どこで」「どのくらい」を定義し直す作業だと捉えると、行動に落とし込みやすくなります。
家族・介護・健康の三角測量
65歳以降は、親の介護や配偶者の健康、孫育てへの関わりなど、家族イベントが仕事の設計に影響しやすい時期です。柔軟に働くためには、介護が必要になったときの連絡網や費用感、地域資源の把握を前倒しで進めておくと、いざというときの意思決定が速くなります。情報の入口としては「介護と仕事の両立・はじめの準備」が役立ちます。
健康は最大の生産性です。研究データでは、適度な運動や十分な睡眠、禁煙が慢性疾患の予防や死亡リスクの低下に寄与することが繰り返し示されています。世界的なガイドラインは中強度の運動を週150〜300分程度推奨し、筋力トレーニングを週2回組み合わせることを勧めています[15]。65歳以降も働く選択を現実にするなら、40代の今から体力の貯金を始めるのがいちばんの近道です。睡眠と回復の整え方は「睡眠と運動のベーシック」もチェックしてみてください。
メンタルヘルスへの予防投資も欠かせません。退職や役割の変化は、小さな喪失感を連れてきます。自分の価値を「会社の肩書」だけに置かず、「助けられる人がいる」「任される役割がある」という多元的な拠り所を意識的に作っておくと、仕事の強度を上下させながらも自己効力感を維持しやすくなります。コミュニティやボランティア、趣味のプロボノなど、緩やかな関わりの場をもっておくことは、働き続ける体力と心のバッファを同時に育ててくれます。
まとめ:65歳以降を「選べる」自分へ
65歳以降も働く人が増える時代に、私たちが目指したいのは、やむなく働くのではなく**「働き方を選べる状態」**です。年金の受給開始、在職老齢年金、税・社会保険、そして資産運用。この4つの歯車が噛み合うと、可処分所得と時間の自由度は同時に改善します。まずは年金の見込額を取り寄せ、現職での役割の磨きどころを上司と話し、社外の小さな仕事を一つ試してみる。そんな小さな一歩が、10年後の選択肢を大きく変えます。あなたは65歳の朝、どこで、誰と、どんな時間割で働いていたいですか。今日の一手を、未来の自分にプレゼントするつもりで選んでみてください。
参考文献
[1] 内閣府. 令和6年版 高齢社会白書 第1章 第2節 高齢者の就業. https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_2_1.html (2025年8月アクセス) [2] 厚生労働省. 改正高年齢者雇用安定法について(令和3年4月1日施行). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html (2025年8月アクセス) [3] 厚生労働省 e-ヘルスネット. 平均寿命. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html (2025年8月アクセス) [4] 内閣府. 令和6年版 高齢社会白書 第1章 第2節 健康寿命. https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_2_2.html (2025年8月アクセス) [5] Geriatr Gerontol Int. PubMed ID:39557426(高齢者の社会参加と認知・メンタルの関連に関する研究). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39557426/ (2025年8月アクセス) [6] 世界保健機関(WHO)/国際労働機関(ILO). 長時間労働が脳卒中と虚血性心疾患による死亡を増加させる(ニュースリリース, 2021年). https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo (2025年8月アクセス) [7] 日本年金機構. 老齢年金の繰上げ・繰下げ. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html (2025年8月アクセス) [8] 日本年金機構. 在職老齢年金(65歳以上). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421-02.html (2025年8月アクセス) [9] 日本年金機構. 在職定時改定の実施について(2022年4月から). https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0420.html (2025年8月アクセス) [10] 厚生労働省. 後期高齢者医療制度の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195866.html (2025年8月アクセス) [11] 日本年金機構. 70歳以上被用者該当届(70歳以上は厚生年金の被保険者とはならない旨を含む). https://www.nenkin.go.jp/service/jigyosho/kousei/hihokensya/20150428-01.html (2025年8月アクセス) [12] 日本年金機構. 短時間労働者の適用拡大について(お知らせ). https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/1001.html (2025年8月アクセス) [13] 金融庁. 新しいNISA(2024年スタート). https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html (2025年8月アクセス) [14] Int J Environ Res Public Health 2022; PMC9727210(仕事の自律性と心理的ウェルビーイングの関連を示す研究). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9727210/ (2025年8月アクセス) [15] 世界保健機関(WHO). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour(2020). https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128 (2025年8月アクセス)