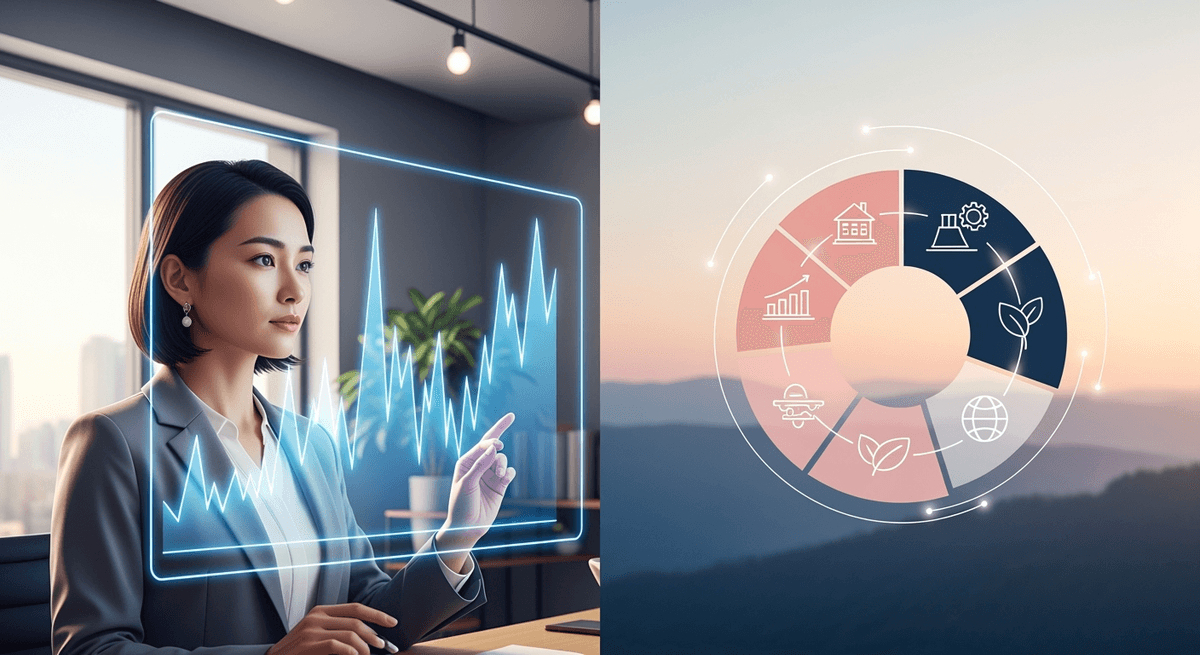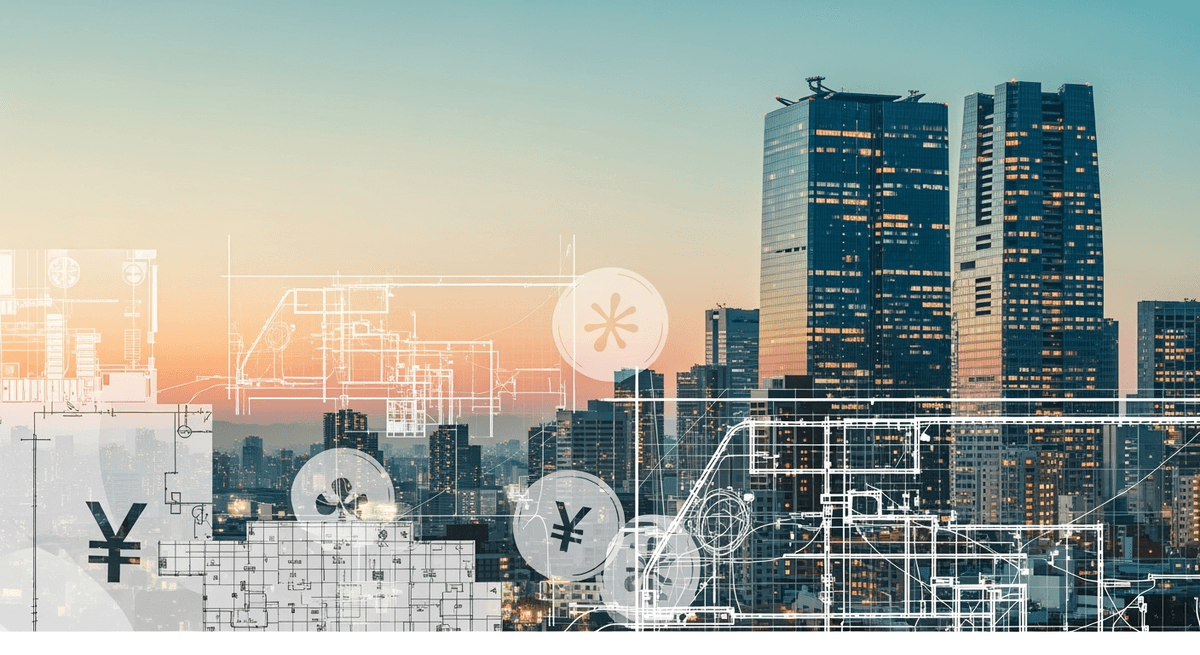掛け捨てと貯蓄型の本質:何を買うか
生命保険の世帯加入率は約9割というデータがあります(生命保険文化センター)[1]。一方で、長く続いた低金利により、貯蓄型保険の予定利率は下がり、貯蓄効率はかつてほど高くありません(日本銀行の金利推移)[2]。編集部が公開資料と概算試算を照合すると、同じ保障を得るコストと、手元の貯金を育てるスピードに、見過ごせない差が生まれる場面が見えてきました。期待と不安が同居しがちなゆらぎ世代にとって、保険に“貯める”を求めるのか、それとも“守る”に徹して貯金は自分で育てるのか。きれいごとだけでは片づけられない、この現実的な選択を数字でほどいていきます。
保険は「大きすぎる損失リスクを、手の届く保険料で移転する仕組み」です。掛け捨てはこの機能に特化し、必要な期間だけ大きな保障を得るための“純保険”。一方の貯蓄型は、保障に“貯める”要素を足したパッケージです。保険料の一部が積み立てられ、将来解約返戻金や満期金として戻りますが、その代わりに毎月の負担は重くなります。
研究データではなく市場慣行の話として、低金利期は保険会社が運用で増やせる期待値が下がるため、返戻率は抑えられがちでした。逆に金利が上がる局面では返戻率の改善が期待されますが、タイムラグもあります。つまり、貯蓄型は“金利環境の影響を受ける金融商品”でもあるのです[2]。ここを理解すると、どちらが優れているかという二元論ではなく、「何を買いたいのか」「いまの金利環境で合理的か」という視点に切り替えやすくなります。
数字でみる違い:編集部の概算試算
仮に、35歳・非喫煙の女性が「子どもが独立するまでの20年、万一のときに3,000万円を遺したい」と考えるケースをイメージします。具体的な保険料は健康状態や商品で変わりますが、編集部で市況水準をもとに概算すると、掛け捨ての定期保険で月額5,500円前後、20年総額で約132万円。これで3,000万円の大きな保障を期間限定で確保できます。対して、貯蓄型で同額の死亡保障を持つのは現実的ではないため、例えば死亡保障1,000万円の終身型を想定すると、月額は2万5,000円前後、20年で約600万円の払込。20年時点の解約返戻金は商品により差がありますが、低金利期の設計だと概ね450万円程度に収まるイメージも珍しくありません。この場合の内部収益率は年0.数%台から1%前後にとどまりやすい印象です。
同じ前提で、掛け捨てとの差額である月1万9,500円を“自分の貯金・投資”として積み立てた場合を考えます。年率3%で20年積み立てできたなら、将来価値は約629万円、うち元本468万円、運用益はおよそ161万円となります。つまり、掛け捨てで大きな保障を押さえながら、差額を貯金・投資で育てる戦略は、流動性を確保しつつ最終到達額でも十分に競り合える可能性がある、というのが編集部の暫定結論です。もちろん、投資は元本割れリスクがあり、想定利回りを下回ることもあります。保険の返戻金は契約に沿ってほぼ確定的に積み上がるという違いもあります。だからこそ、自分の心理と家計の“耐性”に合わせた選び方が重要になります。
貯金の居場所を先に決める:安心と自由のバランス
保険選びの前に、そもそもの貯金の置き場所を設計しておくと、判断がブレにくくなります。毎月の生活費の数カ月分はすぐ使える普通預金や定期預金で確保し、突然の出費や収入減に備える層をつくる。ここは「守りの貯金」です。その上で、5年以上使わないお金は新NISAなどの長期・分散の器に入れて増やすことを検討する。「攻めの貯金」は時間を味方にする設計が向いています。新NISAは生涯非課税枠1,800万円という制度設計が特徴で、長期・積立・分散に適した公募投信を選べますが、値動きリスクは避けられません[4,5]。預金は目減りしにくい一方で増えにくい、投資は増減するが長期ではリターンが期待できる。この二者を混ぜるレシピを家計側で先に決めておけば、貯蓄型保険の“貯める”部分をどこまで取り込むののかが具体的に見えてきます。
流動性も見逃せません。貯蓄型は契約初期の解約返戻金が小さく、短期でやめると元本割れしやすい構造があります[3]。転職や介護、離婚や再婚、住み替えなど、ゆらぎ世代にはライフイベントが重なりがちです。将来の不確実性が高いと感じるなら、掛け捨てで保障を確保し、余力を貯金と投資で柔軟に動かせるようにするほうが、心理的な自由度を保ちやすいこともあります。逆に、「この保険を老後まで絶対に持ち続ける」という強い意思と資金計画があるなら、貯蓄型の強みである長期の返戻も生かしやすくなります。
編集部の視点:家計の“見えない固定費”にしない
毎月の保険料は、固定費の顔をした投資判断です。積み立てられているからと安心しているうちに、実は機会費用が膨らんでいるというケースもあります。契約更新時に保険料が跳ね上がった結果、家計に圧力がかかり貯金が止まるなら本末転倒です。逆に、掛け捨てで浮かせた分をなんとなく消費してしまうのもよくある落とし穴。ここは仕組み化が有効で、保険料の引き落とし日に合わせて差額を自動で別口座や積立投資に回すと、意思のコストを下げられます。
貯蓄型が活きる条件と、気をつけたい点
貯蓄型がフィットするのは、遺すニーズに「確実性」を求めるときや、資産の一部を保険会社の与信で守りたいときです。例えば、相続で現金に換えやすいまとまった保険金が役立つ場面や、保険料払込免除の特約を付けて就業不能時の払込リスクを抑えたいケースなど、機能としての価値が明確にある状況では選択肢に入ります。金利が上向く局面で設計された商品の返戻率が相対的に良くなることもあるため、タイミングと商品の“設計時期”を確認する視点も有効です[2]。
一方で、気をつけたいのは流動性とコストの二つです。中途解約のペナルティを織り込んだうえで、他の手段(定期預金、新NISAの長期積立など)と比べたときの期待リターンや自由度を、家計の現実と並べて評価したい。さらに、死亡保障額を大きくしたいのか、老後資金を積み立てたいのか、目的が混線していないかを点検すると、商品選びのミスを減らせます。保険で“貯める”のはあくまで手段であって、目的は家計の安全度と選択肢を増やすこと。ここを見失わないことが、後悔の少ない契約につながります。
金利と家計の二重チェック
金利動向はコントロールできませんが、チェックはできます。商品パンフレットの予定利率や返戻率の想定、設計書のIRR(内部収益率)を確認し、家計の想定利回りと比べる。例えば、家計側では「攻めすぎない想定」として年2〜3%を目安に差額積立の計画を置くのか、もっと保守的に年1%相当の定期預金運用で考えるのか。どの前提でも、掛け捨てで大きな保障を押さえ、差額を貯金で担保する戦略は比較の基準軸になります。
選び方の流れを一本の道にする
方法論はシンプルです。最初に、必要保障額を言葉で定義します。住宅ローンの残債、子どもの教育費、葬儀・住み替えなどの一時費用、当面の生活費。これらの合計から、遺族年金や企業の保障、すでにある貯金・運用資産を差し引いて、残る不足分を保険で埋める。次に、その不足が存在する期間を見極めます。子が独立するまでなのか、定年までなのか、あるいは一生涯なのか。期間が定まれば、掛け捨てでどこまでカバーし、どこから貯蓄型を検討するかの境界が見えてきます。
並行して、月額予算の上限を決めておきます。ここでの注意点は、保険料を増やすほど貯金・投資に回る余力が細り、流動性が落ちるというトレードオフを意識することです。試算上は成立しても、実生活では子の進学や親の介護、住居のメンテナンスなど、臨時の支出は想像以上に発生します。固定費を上げすぎないことが、防衛力の高い家計の共通点です。
最後に、商品選びです。複数社の設計書で同条件を取り寄せ、掛け捨ての更新時の保険料、貯蓄型の返戻率の推移、特約の中身とコストを横並びで見る。迷ったら、掛け捨てで中核保障を固め、差額を自動積立で“先取り貯金”する設計を仮置きにし、そこから貯蓄型の必然性がある部分だけを足し算するやり方が、情報過多な時代でも破綻しにくい進め方です。
編集部のケース試算と、小さな結論
冒頭のケースに戻ると、掛け捨てで3,000万円の保障を20年確保しつつ、月1万9,500円を貯金・投資に回すと、20年後に約629万円の到達点が見込めます(年3%想定)。一方、貯蓄型で月2万5,000円を20年払って約450万円の返戻と仮定した場合、到達額自体は前者に分があります。保障は掛け捨ての方が大きく、流動性も高い。もちろん、想定利回りを下回れば差は縮みますし、貯蓄型の“契約どおりに積み上がる安心”を評価する人もいるでしょう。だからこそ、結論は一つではありません。ただ、編集部としては**「大きな保障は掛け捨てで、増やす設計は家計側の貯金・投資で」**を標準形に据え、貯蓄型は目的が明確な部分だけに絞る、という方針をおすすめしたいと考えています。
関連して、家計全体の設計を学び直したい方は、家計の固定費を整える基礎記事も役立ちます。例えば、固定費リセット術、制度活用の観点では新NISAの始め方、保障の基礎を確認するなら生命保険の基礎も参考にしてください。どれも貯金と保障の“境界線”をクリアにするための材料になります。
まとめ:いま守り、先で自由になるために
私たちの毎日は、思い通りにいかない出来事の連続です。だからこそ、備えはシンプルでタフな設計にしたい。掛け捨てで“いま失えないもの”を守り、余力は貯金と長期の器で育てる。貯蓄型は、目的がはっきりしているところにだけ丁寧に使う。この順番で考えると、迷いが減り、選んだ理由に納得が残ります。金利や市場は動きますが、私たちが握れるのは、毎月のキャッシュフローと意思決定の順番です。
今日できる小さな一歩は、加入中の保険証券を並べて“目的”を書き添えること。それが保障なのか、将来の貯金なのか、両方なのか。目的が言葉になったら、必要保障額の再計算と、差額の自動積立の設定まで一気に進めてみる。来月の通帳に小さな変化が刻まれたら、それは大きな選択の第一歩です。次に読むなら、家計の見取り図を描くための家計マップ作りへどうぞ。あなたの“いま”に合う設計は、きっと見つかります。
参考文献
- 生命保険文化センター(JILI). 生活保障に関する調査・プレスリリース(2024年). https://www.jili.or.jp/press/2024/9770.html
- ニッセイ基礎研究所. 生命保険の世帯加入率の変化と低金利の影響に関するレポート. https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id%3D79148?pno=2&site=nli
- マニュライフ生命. 終身保険の基礎と解約返戻金の注意点(コラム). https://www.manulife.co.jp/ja/individual/about/insight/column/article/syushin_column06.html
- 三井住友銀行. 新NISAの制度解説(非課税保有限度額1,800万円 ほか). https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/nisa2024/0006/
- ダイヤモンド・ザイ. 新NISAのポイント解説(生涯非課税1,800万円・投資枠の構造). https://diamond.jp/zai/articles/-/1026885