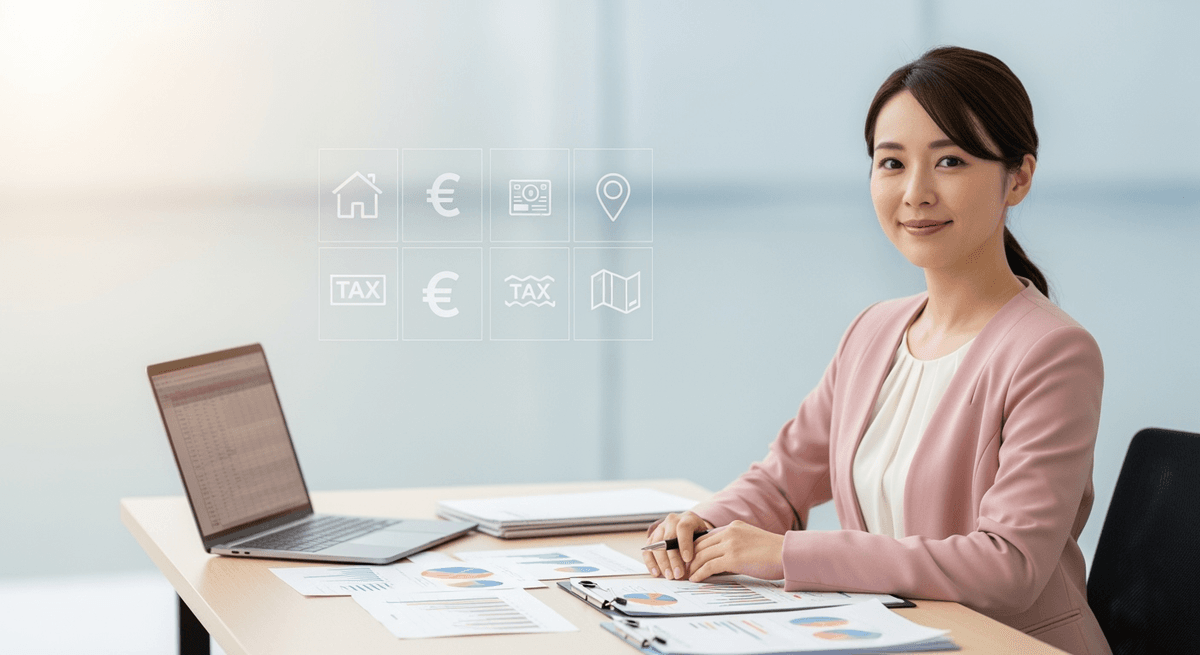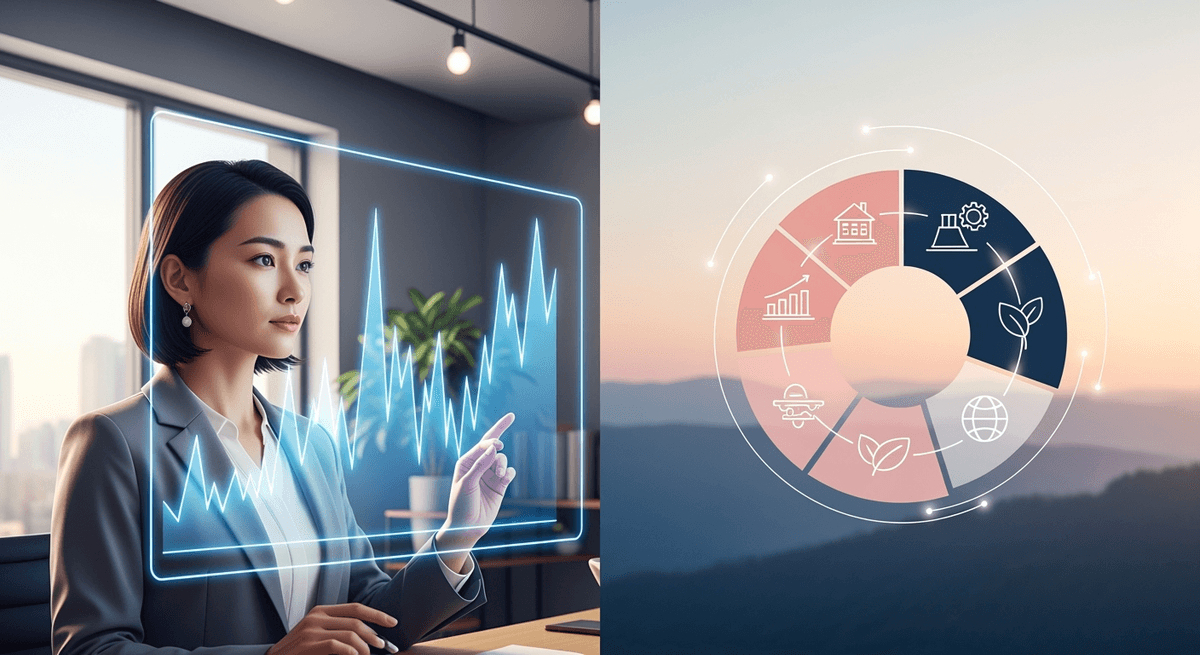学資保険の強みと限界を数字でとらえる
日本政策金融公庫の調査では、大学進学時に必要な入学費用は平均で100万円を超え、在学中の教育費も年間で100万円前後に達する傾向があるとされています[1]。文部科学省の統計でも、公立・私立の別にかかわらず学習費は右肩上がりの局面が続いています[2]。編集部で各種データを横断的に確認すると、子の進学に向けた準備は「早く・長く・仕組み化」が効く一方で、物価上昇に負けない視点が欠かせないという現実に行き着きます。
とはいえ、日々の家計は有限です。固定費、キャリアの転機、親の介護など、私たちの生活は「理想どおりに積み立て続ける」ことを許してくれない時期もやってきます。そこで焦点になるのが、学資保険という保険の枠組みで守るのか、投資信託などで投資の力を借りて増やすのか、あるいはその配分をどう決めるかという問い。この記事では、学資保険と積立投資を、使えるデータと具体的な試算でフラットに比較し、貯金・投資・保険のバランス設計を一緒に考えます。
返戻率と保障のリアル
学資保険は、満期や進学時期に合わせて給付金が受け取れる貯蓄性保険です。最大の魅力は、契約者(親)に万一があった際に以後の保険料支払いが免除され、予定どおり給付が継続される「保険料払込免除」という仕組みにあります。これは投資でも銀行の貯金でも代替が難しい保障機能です。一方で、低金利が長く続いた日本では、学資保険の返戻率は概ね100〜110%程度にとどまる商品が中心で、契約年齢や払込期間、給付タイミングによっては100%を下回る時期もあります。元本割れリスクは主に「途中解約」に潜み、解約返戻金が払込総額を下回る設計期間が長い点も見逃せません。
返戻率は「受取総額÷払込総額」で表せます。例えば月1.5万円を15年間払って合計270万円、18歳から給付金総額が285万円なら返戻率は105%です。研究データや市場金利の推移を踏まえると、予定利率の上昇局面で商品性が改善する余地はありますが、保障コストが内包される以上、長期の期待リターンは投資より抑えめで設計されます。ここで重要なのは、学資保険は「増やす道具」よりも「目的に確実に届かせる道具」という位置づけだと理解しておくこと。払込免除が必要か、給付のタイミングが進学イベント(入学金・授業料納付)に合っているかまで含めて、家計の安全装置として評価するのが現実的です。
キャッシュフローと税制の小さな追い風
学資保険は支払いが半強制的に続く設計なので、忙しい時期でも「気づけば積み上がる」という効用があります。また、契約内容によっては生命保険料控除の対象になり、年末調整や確定申告で所得控除が受けられます[6]。控除は手取りに効く実利で、数千円〜の還付が毎年積み上がれば体感も小さくありません。ただしインフレ耐性という観点では、固定の満期金は物価上昇に連動しないため、教育費が上がる局面では実質価値が目減りします。ここが「増やす力」を持つ積立投資との差分になります。
積立投資の可能性と怖さを同時に扱う
投資信託を用いた積立投資は、世界の株式や債券に広く分散しながら時間を味方にするアプローチです。研究データでは、広く分散した株式の長期リターンは年率4〜7%程度、債券は1〜3%程度、株と債券のバランス型で2〜4%程度のレンジが示されることが多く、物価上昇を上回る可能性を持ちます[3]。さらに2024年に刷新された新NISAは非課税期間が無期限のため、教育資金のような18年前後の長期目的とも相性が良好です[5]。課税口座で得た運用益には約20%の税金がかかりますが、NISAならこの負担を回避できます。
18年の時間分散がくれる期待値
ドルコスト平均法で毎月コツコツ買い付けると、高い時には少なく、安い時には多く買うことになり、取得単価が平準化されます。相場の短期的な上下動は避けられませんが、積立期間が10年以上になるとプラスに着地する確率が高まるという統計が複数の市場で確認されています[7]。教育費のピークは入学金支払いが集中するタイミングなので、必要時期が明確な資金は3年前からリスク資産の比率を落とすなどの着地設計を組み込むと、価格変動の直撃を和らげられます[7]。
下落相場と「途中でやめない」工夫
怖さの本質は価格の変動にあります。マイナスの月は必ず訪れますし、その時に積立を止めてしまうと期待値が崩れます。そこで、口座を自動積立に設定して「意思の力」に依存しない仕組みにする、家計の緊急資金を6か月分ほど別枠で確保して投資口座に手を触れない、受験直前の資金は現金や個人向け国債に移す、といった運用と家計の連携を日頃から整えることが、結局は最大のリスク管理になります。気持ちが折れそうな時に役立つのはルールです。投資は「やる/やらない」の意思決定ではなく、「どう続けるか」の設計だと捉えると迷いが減ります。制度や積立の始め方は、基礎から整理したNISA超入門の記事も参考になります。
試算で比較:18年の差と心の余白
具体的にイメージしてみます。子どもが現在0歳、18年後の進学を目標に毎月1.5万円を用意したとします。現金の貯金で年利がほぼゼロなら、積み上がるのは単純に324万円です。学資保険で返戻率105%の設計なら、払込総額324万円に対して受取総額は約340万円。一方、投資信託の積立で年率3%のリターンが得られた場合、複利で約430万円。年率5%のケースでは約525万円まで到達することもあります。もちろん投資は元本保証ではなく、受験直前に大きく値下がりするリスクもありますが、長期・分散・積立の三点を揃えた運用は、統計的には正の期待値が確認されています[7]。
数字の差は、進路の選択肢を増やす「心の余白」に直結します。例えば私立の初年度納付金が想定を超えた、下宿が必要になった、留学を検討した、といった変化に対して、手元資金にバッファがあるかどうかは心理的な安心にも響きます。逆に、家計の安全装置として払込免除のある学資保険をベースに置くことで、「親に万一があっても教育資金だけは守れる」という安心もまた大きい。編集部としては、どちらが絶対的に優れているというより、守る力(学資保険)と増やす力(積立投資)を目的に応じて配分するという考え方が、ゆらぎの多い40代の家計にフィットすると感じています。
配分の決め方は、まず目標額と時期を言葉にし、家計の固定費・変動費・余力を棚卸しして、「最低限のライン」と「理想ライン」を分けて設計すると腹落ちします。最低限のラインは、入学金や前期授業料など期日が固定の支払いに対応する金額で、ここは学資保険や定期預金で確保する。理想ラインは、在学中の費用や選択肢を広げるための上乗せ部分で、ここをNISAを活用した積立投資で狙う。こうして二層に分けると、途中の環境変化にも調整しやすくなります。家計の見直しは固定費の整え方、保険の基礎は保険の見直しガイドもあわせてチェックしてみてください。
ケーススタディ:40歳・子2歳のご家庭
例えば40歳の共働き、子ども2歳。18年で目標400万円を最低ラインとして設定し、学資保険で200万円を確実に、残りをNISAでの積立投資で目指すという配分を考えます。学資保険は払込免除付きで15年払込にして、給付金は高3と大1に厚めに設定。投資は全世界株式の低コストインデックスを中核に、受験の3年前から債券比率を高めてボラティリティを落とす着地設計にします。毎月の積立計画は、ボーナス月だけ少し多めにするなど季節性も織り込むと、家計のストレスが減ります。途中で保育料が下がる、住宅ローンの金利が変わる、といったライフイベントの度に配分を見直せるのも、二層設計の利点です。投資の制度変更や銘柄選びで迷うときは、編集部の長期投資のはじめ方も役立ちます。
まとめ:選ぶより配分、そして見直す
学資保険は**「確実に届かせる」力、積立投資は「インフレに負けにくく選択肢を増やす」**力を持っています。揺らぎの多い40代の家計にとっては、どちらか一択ではなく、目的を分けて配分することが現実解になりやすい。まず必要時期と最低限の支払いを言語化し、守る力で土台を固めたうえで、増やす力に時間を味方につけてもらう。途中のキャリアや家族の変化に合わせて、年に一度の「配分点検」を習慣にすれば、軌道修正は怖くありません。
18年は長いようで、動き出せば味方になる十分な時間です。今日、できる最初の一歩は、口座や証券会社を選ぶことでも、完璧な商品を見つけることでもなく、目標額と使う時期を書き出すこと。その紙を冷蔵庫に貼るだけでも、次の行動は自然と決まります。
参考文献
- 日本政策金融公庫「教育費はいくら必要?かかる目安額をご紹介」https://www.jfc.go.jp/n/finance/ippan/kyoikuhi/cost.html
- 文部科学省「学習費調査」関連ページ https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/006/05120501/003.htm
- 時事ファイナンシャル「長期投資コラム:主要アセットの円ベースの期待リターン」https://financial.jiji.com/long_investment/article.html?number=446
- 野村證券「新しいNISA(2024年〜)概要」https://www.nomura.co.jp/retail/nisa/nisa-2024/
- フコク生命「学資保険は生命保険料控除の対象になる?」https://www.fukoku-life.co.jp/plan/tsubasa/basic/trivia16/
- 金融庁 NISA特設サイト コラム「心とお財布が幸せに!お金との付き合い方」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/column/column-10.html